
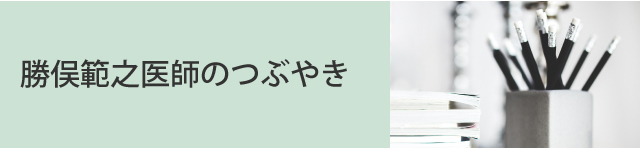
※このページでの勝俣先生のお話は先生の承諾を得て作成させていただいています。
日本医科大学武蔵小杉病院腫瘍内科教授

免疫チェックポイント阻害剤アベルマブ、非小細胞肺がんに対して、ドセタキセルに比べて、有効性示せず。
こういったNegative 試験の結果もきちんと報告することが大切ですね。
正しく臨床試験をやり、有効なのか、無効なのかをしっかりと示すことが最も患者さんのためになることと思います。
このことをしっかりと報道できるメディアが日本には非常に少ないのが残念なことです。
本庶先生は、正しい、本物の免疫療法の開発に至ることとなった基礎研究をされました。
世の中には怪しい免疫療法がたくさんありますので、注意が必要です。
多くの場合、免疫療法は現在科学的エビデンスが十分に検証されていない状態にある。
免疫療法をネットで検索すると、怪しい情報が満載です。
緩和ケア病棟をもちながら、インチキ免疫療法やっている施設がある。これは、さすがにまずいと思います。
免疫力アップとか、自分の免疫力を高めるとか、免疫療法というのは、そんなに安易なものではありません。
がん免疫療法の正しい知識。米国国立がん研究所(NCI)ファクトシート より。
世の中には、インチキな免疫療法などあふれていますが、こちらが正しい情報です。
「乳がんの90%は早期発見で治ります」などという、検診のキャンペーンの文言をよく見かけるが、これはまったく誤解を招く表現だと思う。
過剰な検診キャンペーンはやめるべき。検診でメリットを得られる人は一部の人のみ。
検診で見つかった多くの早期がん患者さんは、過剰診断された可能性がある。進行がん患者さんの多くは、「検診しなかったから進行してしまった」のではなくて、「検診に向かなかったがんであった」可能性がある。
もちろん、日本は、がん検診率が低いので、検診率を上げるために、ある程度の啓もうも必要であろうが、啓もうだけで、検診率が上がらず、限界があることは周知のこと。
検診率を上げるためには、コールリコール(受診者へ何らかの方法で、再度受診を呼びかけること)をするべきなのです。
がん検診における、死亡率低下の大切さの意味、過剰診断・治療の不利益についても、正しく情報提供をしている専門家の先生方は、意外と少ないので、残念に思っています。
がんには、検診に向かないがんも多い。急速に進行するがんは、検診には向かない。乳がんや肺がん、大腸がん、胃がんなどの固形がんでも、急速に進行するがんがある。また、ゆっくり進行する超のんびりがんは、検診すると、過剰診断となり、過剰治療となる。
>> がんを正しく恐れること(下)~検診に向かないがんもある~
乳がん検診について、コクランのシステマティックレビューより。2,000人検診を受けると1人(0.05%)乳がん死亡を減らし、200名に偽陽性、10人に過剰診断・過剰治療。
ガイドラインに書いてある引用文献、エビデンスは、最低限のもの。ガイドラインさえすればよい、ガイドラインだけすればよい、という代物ではない。
実際の臨床現場では、ガイドラインだけで治療できるというものではない。ガイドラインをベースに応用していくのが実際の診療。
ガイドラインだけやっていくのは、初心者レベル。ガイドラインには引用されていないけど、ガイドラインにも書いていないような、レベルのエビデンスにもすごく精通していて、患者さんに応用していくのが、プロのレベルと思います。
ガイドラインも読まない、ガイドラインに従わないのは論外。
卵巣がんで、再発しても、延々と効いているからと、TC療法のみやっていくのは止めてほしい。
神経毒性が蓄積毒性としてたまっていき、歩行不能になった患者さんがいます。
ガイドラインにも、プラチナ感受性再発には、プラチナ製剤を含む多剤併用療法としてオプションが書いてあるのに。
腫瘍内科医は、「ケモ屋(化学療法だけをする医師)」になってはいけない。
化学療法以外の選択肢もきちんと患者さんに提案できる治療コーディネーターとなるのがプロの腫瘍内科医。
臨床試験の成功率、第一相試験3.4%、第二相試験だと6.7%、第三相試験でも35.5%です。そんなに簡単に成功するものでない。
よくメディアで、動物実験が終わり、臨床応用が期待などと、大げさな報道をするが、臨床試験で成功するのは簡単ではない。
なったとしても、第三相試験までやらないと、本当に良いかわからないし、承認もされないということなのです。
ましてや、臨床試験もやっていないようなレベルの治療法は論外。
胚細胞性腫瘍は、若年者に多いが、化学療法のみで治癒可能な希少がんです。ただ、診断、治療がきちんと行われていないことが多い。特に、性腺外原発の胚細胞腫瘍は診断、治療がひどい状況。
がん専門病院でもきちんと治療が行われていない現状がある。特に女性の胚細胞性腫瘍の場合、初回標準治療のBEP療法でさえ、標準的投与量でなかったり、すぐに減量、延期などを繰り返されたりすることが多い。好中球の値に関係なく、減量、延期せず、dose intensityを保つことが大切。
がんとの付き合い方。三つのあ。あせらず、あわてず、あきらめず、が大切。
つい、がんと診断されるとあせってしまいがちだが、一番、あせっていて、患者さんをあせらせているのは医者じゃないかと思う。
がんになっても、あきらめない、ことも大切。これは積極的治療をあきらめない、ということでなくて、自分の人生をあきらめない、大切ないのちをあきらめない、ということだと思う。
大阪地震、一部の病院で治療が困難になっている病院もあるかと思います。災害時にがん患者さんが気をつけることについて、ヨミドクターに以前まとめたものがありますので、ご参照ください。