
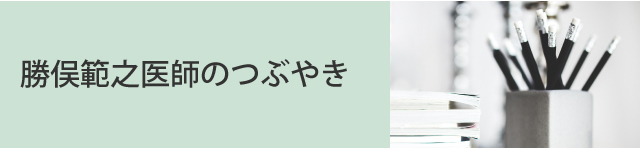
※このページでの勝俣先生のお話は先生の承諾を得て作成させていただいています。
日本医科大学武蔵小杉病院腫瘍内科教授

朝日新聞朝刊にコメントを掲載していただきました。
臨床試験に詳しい日本医科大学武蔵小杉病院の勝俣範之教授(腫瘍内科)は言う。
「科学的に有効性が示されて初めて薬は承認される。これが基本。ヒトを対象にした試験が成功する可能性は低く、結果が出る前に承認への言及があることそのものがおかしい」
日本では製薬企業主導の試験が多く、米国のように研究者によるものが少ないことも問題視する。
「コロナを機に、臨床試験を推進し、正しい情報発信をする 機関を作るなど根本的な見直しをすべきだ。政治から独立した機関を設け、質の高い臨床試験ができる環境を整えてほしい」と話す。
医療のニセ情報、がんに限らず、新型コロナでも多い。
ニセ情報は患者さんの大切な命を奪うことにもなります。ニセ情報を放置するのは良くないと思います。
コロナに便乗して、ニセ医学で商売しようとするのは許せないことと思います。
がんに便乗してニセ医学で患者さんを騙して商売する構図と似てますね。
がんにもさまざまな種類があり、中には、進行しないがんもある。ある患者さん、10年経過観察したが進行しなかった。
「おとなしいタイプのがんで良かったですね」と言うと、患者さん、「実は、玉川温泉の布団を使ってたんです。それが効いたように思います」と。
これは、医学用語で、交絡バイアスと言います。実は別な要因が寄与しているのに、因果関係ありと思いこんでしまうバイアスです。
長い間がん患者さんを診ていると、自然治癒の患者さんにも遭遇します。
ある子宮体癌の再発患者さんは、腹水もたまっていましたが、抗がん剤始める前に、腹水が消えてしまいました。
私は内心「世紀の発見をした」と思い、その人にこれまで何かされたのか?根ほり葉ほり聞いたのですが、「これまでと変わらず普通の生活してました」と。
調べてみると、がんの自然治癒は年間20例くらいは報告があるんですね。
ある有名な○○式食事療法を開発した方は、進行腎臓がんだったそうですが、腎臓がんは、最も自然退縮の報告が多いがんです。
私も自分の患者さんで一人経験があります。
交絡バイアスには気を付ける必要があると思います。
コロナがだんだん大変になってきて、皆イライラしてきている。
困難な状況になった際に、どう対応するか大切。
ここでも、最善を期待し、最悪に備える、ことが大切と思う。
こんな時だからこそ、自分にも優しく、人にも優しく。
がんになると、なかなか主治医に意見したり、質問したりできないものです。
「主治医に遠慮することより、自分の命に遠慮しないことのほうが大事」「わがままな患者になる」などとアドバイスしたりします。
高橋都先生は、患者さんは「女王様になるのよ」と言ってましたが、とかく日本人は控えめですので、そのくらいの気持ちでいていいのだと思います。
がんの標準治療も理解されていないが、臨床試験はもっと理解されていません。
ランダム化比較試験は、最終段階の臨床試験で第三相試験とも呼ばれます。
これまでのチャンピオンの標準治療と、新治療との最終決着戦です。
標準治療群と新治療群にランダムに分けられますが、標準治療になったからといって、「はずれ」ではありません。
これまでのチャンピオン治療なのですから。
新治療が負けることもよくある。
おおざっぱに言うと、新チャンピオンが生まれる可能性は、36%です。
やはり標準治療は強い。
日本人の2人に1人ががんに。
誰でもがんだと診断されれば動揺します。
「何とか治したい」と考える人は多いのですが、「がんと共存を目指していく」という考え方が大切です。
つまり「がんとうまく付き合っていく」と考えてほしいと、患者さんにはいつもお伝えしています。
そのうえで、がんと診断されても慌てないためには正しい情報を知ることです。これに尽きます。
標準治療の重要性などを知らずに「何でもいいからやってみよう」という状態はとても危ない。
あやしい民間療法に手を出しかねません。
がん治療には、民間療法、自由診療などとうたった数多くの治療法が存在します。
その多くがエビデンスがなく、自費診療。
なぜか自費診療は、最新の治療でまだ認可が下りていないものというイメージがあるようですがこれは間違い。
厳しい審査で保険承認された、標準治療が最良だと肝に銘じてください。
ドラッグラグが以前よりも改善。海外との違いについて
日本では海外と比べて、腫瘍内科医が少ないことは大きな問題。
欧米諸国では外科医が抗がん剤を処方することはほとんどないので、今後の課題です。
また、日本はこれまで、薬の認可に時間がかかりすぎて、海外で承認された薬がなかなか使えない"ドラッグラグ"と呼ばれる期間が長かったんです。
日本の製薬会社は優秀で、日本で開発されたにもかかわらず、先に海外で承認されるなんてことも。
これは、厚生労働省の薬の認可機関に医師を増やすなどして対応してきました。
現在は海外とのドラッグラグは1年以内に短縮され、ほぼ解消されています。
仕事をしながらでも治療できる?「抗がん剤」最新事情
全身に薬を巡らせてがんの治療を行う「抗がん剤」。
副作用が強い、効果が疑問視されるなど誤解が多い抗がん剤ですが、現在150以上の種類があり、新しいものも開発されこれまでできなかったがんへの治療も可能になっています。
抗がん剤を投与するために入院することも多いのですが、だんだんと通院で仕事をしながら続けられるように。
個人差はあるものの吐き気、脱毛、免疫力の低下などつらいと言われる抗がん剤の副作用。
最近では副作用を抑える薬も増えています。
腫瘍内科医が、抗がん剤と一緒に副作用に効く薬も処方する支持療法が一般的に。
痛みを我慢してこそ効果があると思いこんでいる人もいますが、副作用を抑えても抗がん剤の効果がなくなることはないので我慢しないでほしい。
副作用の状況についても隠さず、できるだけ主治医に相談を。
がんの専門医である"腫瘍内科医"の必要性とは?
抗がん剤の専門家で、がんを総合的に診断、治療するのが「腫瘍内科医」。
手術を行う外科医ががん専門医だと思われがちですが、腫瘍内科医は、抗がん剤に詳しいことはもちろん、抗がん剤の副作用を軽減するための緩和ケアの知識も豊富。
内科医としてがんを包括的に診ることができます。
海外に比べると、日本には腫瘍内科医が非常に少なく、現在は全国に1330人。
病院に腫瘍内科医がおらず、手術を行った外科医がそのまま担当医として抗がん剤を処方していることも多いのが現状です。